習志野市

習志野市は千葉県北西部の東京湾に面した位置にあり、内陸部の変化ある自然地形と平坦な埋立地から形成しています。首都圏へのアクセスが良く、東京のベッドタウンとして発展しています。谷津干潟や谷津バラ園などの豊かな自然環境に恵まれる環境を活かして、奏の杜と呼ばれる再開発が進められています。
概要
- 面積
- 20.97km2
- 人口
- 176,122人(2022年2月1日)
- 市の木
- アカシア
- 市の花
- アジサイ
- 地図
歴史
旧石器時代から人が定住して谷津貝塚などの遺跡が残されています。中世には千葉氏が治めましたが、後北条氏とともに滅亡して徳川家の支配下になりました。明治時代から騎兵連隊や鉄道連隊が置かれるなど軍都として発展してきましたが、戦後に軍用地は病院や学校に建替えられて宅地が広がりました。
旧石器時代、縄文時代、弥生時代
旧石器時代から人類の痕跡が確認されています。縄文時代には花咲新田台遺跡をはじめとして、実籾3丁目遺跡・実籾霊園遺跡、藤崎堀込貝塚、藤崎3丁目南遺跡などで集落の跡が見つかります。弥生時代には水稲耕作を中心とする農耕が始められましたが、市域に遺跡は確認されていません。
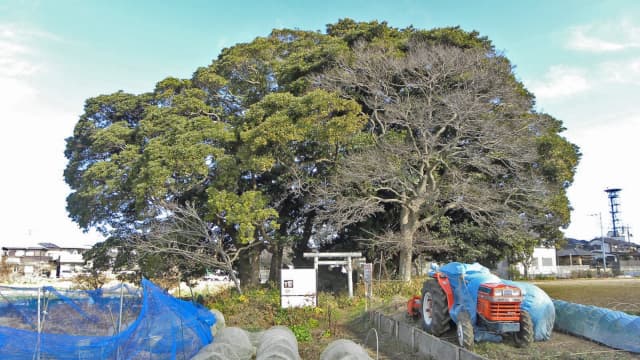
藤崎堀込貝塚
縄文時代中期から後期にかけて形成した貝塚で、縄文時代中期の住居跡や縄文時代後期の土器や石器などが出土しています。
古墳時代、飛鳥時代
鷺沼城址公園周辺に古墳時代後期の6世紀後半の鷺沼古墳が造営されました。実籾霊園遺跡などは柔らかい石で勾玉などの形を小さく加工した工房跡が残されています。
奈良時代、平安時代
谷津貝塚には7世紀末から10世紀前半にかけて大規模な集落が形成しました。治承4年(1180年)に源頼朝が鷺沼御旅館に滞在したとの記録があります。源頼朝は石橋山の戦いで敗れて房総半島に上陸し、下総国の千葉常胤を頼りました。
鎌倉時代、南北朝時代
鎌倉幕府の有力御家人である千葉氏が支配を固め、千葉常胤の三男胤盛が武石氏を名乗り実籾本郷を拠点としました。千葉勝胤の家臣・木村十太夫が配置された記録があります。
室町時代、安土桃山時代
天正18年(1590年)の豊臣秀吉の小田原征伐で後北条氏が滅亡すると、千葉氏もともに滅亡しました。関東には徳川家康が入部し、慶長8年(1603年)に江戸幕府を開府しました。
江戸時代
江戸幕府が開府すると、市域は幕府領または旗本領となりました。海岸沿いの房総往還や東金街道は、幕府の役人や住民の通行や物資輸送で利用され、街道沿いには集落が成長していきました。海上輸送も盛んに行われ、江戸との間を多くの船が行き交いました。東習志野地区は幕府の直轄牧場である小金牧の一部である下野牧に含まれました。
明治時代、大正時代、昭和時代
明治4年(1871年)の廃藩置県で佐倉県ののち印旛県となり、明治6年(1873年)に千葉県に編入されました。この年に陸軍の演習場となる小金牧に行幸された明治天皇が習志野原と命名しています。騎兵第一・第二旅団が設置されるなど軍事都市としても発展しましたが、戦後に旧軍施設を教育施設や住宅などに転用されました。昭和41年(1966年)と昭和52年(1977年)の埋立工事で市域は拡大し、京葉臨海工業地帯の一角を形成する都市となりました。

伊藤新田・谷津遊園跡
明治時代中期から大正時代の初めまで塩田がありましたが、明治44年(1911年)と大正6年(1917年)の暴風雨で閉鎖されて谷津遊園が開園しました。

谷津干潟
埋め立てにより都市の中に取り残された干潟で、国内で初めて水鳥の生息地として国際的に重要とされるラムサール条約に登録されました。
