南房総市

南房総市は、房総半島の南端に位置し、北側には県下最高峰の愛宕山や南総里見八犬伝の舞台である富山が連なります。米作や花卉の促成栽培、野菜の施設栽培、ビワなどの果樹栽培、酪農が盛んです。海女による潜水漁業が行なわれるほか、和田港は関東唯一の捕鯨基地として知られています。
概要
- 面積
- 230.12km2
- 人口
- 32,175人(2022年2月1日)
- 地図
歴史
房総半島の南部にある南房総市は、落ち延びた源頼朝が平家討伐の再起を図る拠点とし、南北朝時代には里見氏が安房国を支配して東京湾の制海権を巡り後北条氏と争う拠点としました。戦時中は東京や軍港横須賀を守る拠点として重要な役割を担いました。
旧石器時代、縄文時代、弥生時代
大房岬遺跡から旧石器時代の遺物が見つかり、大房岬の藤四郎台遺跡や深名遺跡から縄文時代の土器や石器が出土しています。弥生時代の遺跡は縄文時代に比べて規模は小さいものの、岡本川両岸に向原遺跡や大久保遺跡などが点在します。
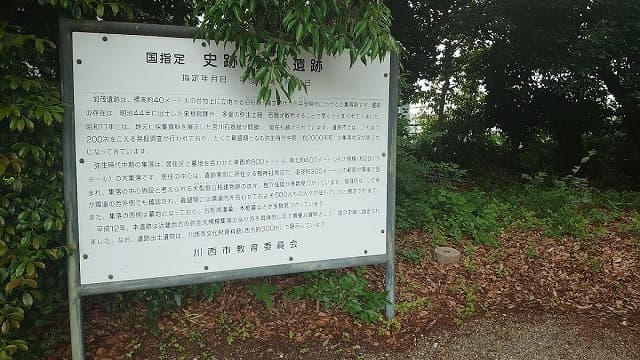
加茂遺跡
丸山川支流の古川沿いに位置する縄文時代前期後半を中心とした遺跡で、割竹形の丸木舟、櫂、丸木弓などの木製品や食料とした木の実や動物の骨などが見つかりました。
古墳時代、飛鳥時代
沖積平野を中心に集落が形成し、現在は消滅しているが大房岬にも大武佐古墳などがつくられました。
奈良時代、平安時代
養老2年(718年)に設置された安房国は、天平13年(741年)に上総国に合併され、天平宝字元年(757年)に分立されました。安房国の中心として国府が置かれ、条里制の遺構も残されています。丸厨房は伊勢神宮の荘園で、豪族の丸氏が守りました。

石堂寺
和銅元年(708年)に恵命と東照が秘宝アショカの王塔を祀る草庵を結んだとされ、神亀3年(726年)に行基菩薩が十一面観世音菩薩を本尊としたと言われます。

弁財天の洞窟
大房岬にある洞窟で、役行者の法力で閉じ込められた海賊が慈覚大師に助けられて金の竜として天に昇り、その抜け出した跡と言われています。

隠れ岩屋(伝説の岩屋)
石橋山の戦いに敗れた源頼朝が武運再興の願掛けをしたときに雨を凌いだ場所で、いつしか深海に棲むという創造の大蛸が海神として祀られました。
鎌倉時代、南北朝時代
安房国は安西氏、丸氏、東条氏、神余氏の豪族で四分されていました。南北朝時代に結城合戦に敗れて房総半島に落ち延びた里見義実は、白浜城を拠点に勢力を広げて杖珠院を菩提寺としました。
室町時代、安土桃山時代
里見氏は安房の武士を従えて着実に勢力を広げましたが、後北条氏と東京湾の制海権を巡り争うようになりました。天正18年(1590年)に豊臣秀吉が小田原征伐を行いますが、里見義康は参陣が遅れたうえに三浦半島や鎌倉方面に進軍した行為が関東惣無事令違反と見なされ、天正19年(1591年)に上総国を没収されて岡本城から館山城へ居城を移しました。

白浜城跡
文安2年(1445年)に里見氏の祖とされる里見義実が、白浜の野島崎に上陸してここを拠点として安房を統一したとの伝説があります。

里見氏城跡(岡本城跡)
東京湾に面した丘陵上に立地しており、天正8年(1580年)に弟の梅王丸との後継者争いに勝利した里見義頼が居城としました。
江戸時代
江戸幕府が成立すると市域は幕府の直轄地として旗本領地となりました。江戸時代末期に外国船が来航するようになると、幕府は大房岬に江戸湾防備の砲台を置きました。

野島崎
房総半島最南端の一角突出している景勝地で、かつては海に浮かぶ島でしたが、元禄16年(1703年)の大地震で陸続きとなりました。

日本酪農発祥地
享保13年(1728年)に8代将軍徳川吉宗がインド産の白牛を嶺岡牧で飼育し、白牛の乳から我が国で初めて白牛酪という乳製品を作りました。

旧尾形家住宅
享保13年(1728年)に建築された居間と土間を別棟にした南方系の分棟型の代表的な民家で、珠師ヶ谷村から石堂寺の境内に移築されました。
明治時代、大正時代、昭和時代
昭和3年(1928年)から翌年にかけて首都防衛の基地として大房岬砲台が設置され、太平洋戦争末期には特殊部隊の兵器実験や訓練場となり、本土決戦用の海軍部隊の重要拠点となりました。

野島埼灯台
明治2年(1869年)に初点灯した房総半島の最南端の岬にある美しい灯台で、関東大震災で倒壊したため、大正14年(1925年)に再建されました。

要塞跡地
旧日本陸軍が昭和3年(1928年)から4年かけて構築した要塞で、地下の鉄筋コンクリート造りには観測所、発電所、照明所、爆薬庫などがありました。
