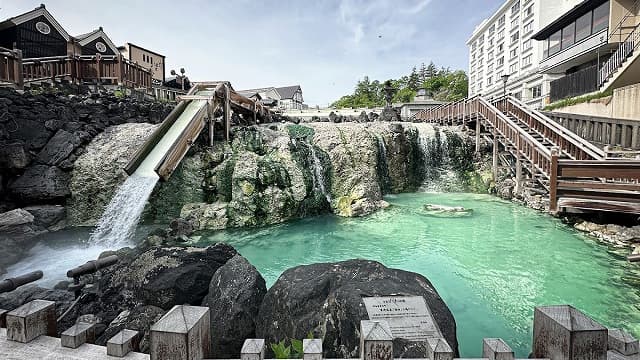吾妻郡
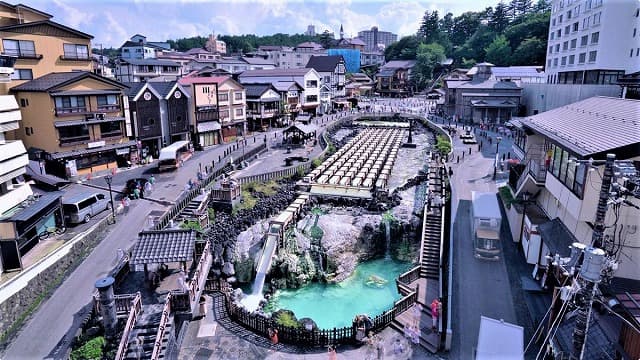
吾妻郡は群馬県の北西部に位置し、草津白根山や浅間山の麓に高原が広がります。吾妻郡を構成する6町村には草津温泉や四万温泉などの温泉があり、多種多様な泉質を楽しむことができます。吾妻川と火山灰土の腐食土壌を活かして嬬恋村のキャベツなど高原野菜が栽培されています。
概要
- 面積
- 1,278.55km2
- 人口
- 50,698人(2021年11月1日)
- 含む町村
- 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町
- 地図
特集
歴史
山に囲まれた吾妻郡は、古くから人が集落を形成し、北関東や信州と活発に交流を行いました。草津白根山や浅間山などの山は信仰の対象となり、霊場として信仰を集めていきました。活火山により日本を代表する有名な温泉地が集中し、江戸時代には草津温泉は天下の名湯として全国に知られ、多くの温泉地が湯治場として大いに栄えていきました。
旧石器時代、縄文時代、弥生時代
高山村に旧石器時代の新田西沢遺跡が残されています。縄文時代には吾妻川流域や名久田川流域で集落が展開し、縄文時代前期の横壁勝沼遺跡や宿割遺跡などで集落跡が見つかりました。縄文時代後期になると遺跡の規模は縮小しつつも吾妻川流域の広い範囲で分布するようになり、弥生時代は長野原一本松遺跡や横壁中村遺跡、有笠山遺跡などで土壙墓などの生活の跡が見つかります。

吾妻峡
関東の耶馬渓とも言われる2.5キロに渡る吾妻川沿いの美しい渓谷です。大昔に火山が噴き出した溶岩を吾妻川が深く浸食してできたものと考えられています。

勘場木石器時代住居跡
縄文時代中期のほぼ円形をした竪穴式住居跡で、中央に炉があり床面はたたき固められています。甕や浅鉢、深鉢及び石斧、石のナイフなどが出土しています。

中山敷石住居跡
縄文時代中期後半から後期前半の敷石住居跡で、中央には石組の炉や平石が廊下状に並べられています。住居跡付近の傾斜地では土器や石器等が出土し、広い範囲に遺跡が展開していました。
古墳時代、飛鳥時代
日本武尊が東征帰途の折に草津温泉を発見したと伝えられます。林宮原遺跡や川原湯勝沼遺跡などで集落が営まれ、6世紀末から7世紀前半にかけて横穴式石室が20以上ある四戸古墳群が造営されました。

姉山の石組カマド
吾妻川左岸段丘上に位置する古墳時代末期の竪穴住居跡に付随する石組竈です。
奈良時代、平安時代
吾妻郡が成立して郡衙が大宮巖鼓神社付近に置かれたとされます。仏教が伝えられて天代瓦窯跡で生産された瓦を使用して金井廃寺が創建し、大和国菅原寺の僧・行基が訪れて草津温泉を発見した伝承もあります。楡木Ⅱ遺跡から9世紀後半~10世紀前半の住居跡が38軒、竪穴遺構3基が検出され、上原Ⅲ遺跡から住居跡のほか鍛冶工房跡が見つかりました。天仁元年(1108年)の浅間山の大噴火で大きな被害を受けました。

熊倉遺跡
白根山麓にある平安時代の集落跡で、石組みの竈と7軒の住居跡が見つかりました。冷涼な高原地帯で寺院建立に必要な弁柄の材料である含鉄土石を採掘する人が住んだとされます。
鎌倉時代、南北朝時代
建久4年(1193年)に源頼朝が草津温泉を見つけた伝承もあります。交通の要衝である吾妻流域の丘陵に 羽根尾城や柳沢城などの城館が造営されました。貞和5年(1349年)に吾妻太郎行盛は南朝方の里見氏に攻められて吾妻川原で自害したとされます。
室町時代、安土桃山時代
永禄6年(1563年)に武田信玄の命を受けた真田幸隆が吾妻太郎斎藤越前守憲広が籠る岩櫃城を攻略しました。岩櫃城には真田信綱が入りますが、長篠の戦いで信綱が戦死して真田信幸が相続しました。

岩櫃城跡
南北朝期に築造されたと考えられています。武田家臣の真田幸隆が攻略して真田家が支配ました。武田勝頼が織田・徳川連合軍から攻められると、武田勝頼を本城に迎えることを提案しました。
江戸時代
真田信幸は中之条町・原町・伊勢町などの町割を完成させ、市場町として栄えました。寛永8年(1631年)に大戸関所が設けられ、寛文2年(1662年)には真田街道と信州街道が交わる大笹宿に大笹関所を設けられました。天明3年(1783年)の浅間山噴火による鎌原火砕流で吾妻川・利根川流域に甚大な被害が出ました。浅間山の大噴火と天明の飢饉で荒廃した地域では、越後の屋根職人が持ち込んだ馬鈴薯の栽培が盛んに行われるようになりました。文政8年(1825年)に殺生河原の硫黄採掘が始まりました。
民衆のヒーロー・国定忠治
博徒の国定忠治は、賭場を荒らして悪行を犯し、国定一家として縄張りを張りました。天保4年(1833年)に天保の大飢饉が起こると、国定忠治は米蔵を解放して村人に配り大衆に愛されました。奇抜な行動を続けた国定忠治は関東取締出役に捕らえられ、罪状が多すぎるため最も重い大戸関所で関所破りの罪として処刑されました。

天明三年浅間やけ遺跡
天明3年(1783年)の浅間山噴火による鎌原火砕流で477名が亡くなりました。鎌原観音堂に逃げた93名は助かりましたが、老婆を背負う中年女性は石段の下で火砕流に飲み込まれました。
明治時代、大正時代、昭和時代
明治時代に生糸が主な輸出品となり富岡製糸場が設立されると、稲作が不向きな吾妻川流域の山の斜面に桑の木が植えられて養蚕が盛んに行われました。昭和7年(1942年)には岩手県沼宮内でキャベツ栽培を学んだ田代地区の青年7名が嬬恋村でキャベツ栽培を始めました。昭和20年(1945年)にアジア太平洋戦争が終結すると、深刻な食糧不足を補うため浅間高原が開拓されて酪農が盛んになりました。平成22年(2010年)の八ッ場ダムの建設により、川原湯温泉がダム湖より高いところに移転しました。

中居屋重兵衛の墓
火力の高い火薬を製造することで成功し、桜田門外の変で使われた短銃を提供したと言われます。日本が開国すると横浜に出店し、上州生糸などの販売で巨利を得たと言われています。