栃木県日光市

栃木県日光市は栃木県北西部に位置します。栃木県全体の4分の1を占め全国の市町村で3番目に広い市です。日光国立公園が広がる自然豊かな土地で、歴史的文化的遺産や温泉などがあり、観光地として世界でも有名な都市です。
- 面積
- 1,449.83km2
- 人口
- 75,330人(2022年)
- 市の木
- もみじ・シラカンバ
- 市の花
- ニッコウキスゲ・ヤシオツツジ
- 市の鳥
- カワセミ・ウグイス
- 市の魚
- ヒメマス・イワナ
- 市民の日
- 3月20日
- 地図
日光市を巡る歴史
日光は日光男体山の古称である二荒山をニコウと呼び日光の文字を充てたとされています。日光が歴史に現れるのは勝道上人が日光山を開山したことに始まります。江戸時代に慈眼大師天海が輪王寺の住職となり、徳川家康の霊廟を建てたことで参拝者で賑わうようになりました。
旧石器時代、縄文時代、弥生時代
日光市は縄文時代や弥生時代の遺跡が16か所発見されています。日光の山が連なる高地であることから、基本的に狩猟の場として使われ、男体山の中腹からは石の鏃が発見されています。
 日本三大名瀑のひとつです
日本三大名瀑のひとつです
 日本屈指の高さにある湖です
日本屈指の高さにある湖です
湯西川地区にある縄文時代中期の仲内遺跡では、23件の竪穴式住居跡と多数の貯蔵穴が発見されました。東北地方南部の影響を受けた独特な囲炉裏や土器が見つかりました。
古墳時代、飛鳥時代
山間部の日光では大きな集落は造られず、古墳は築かれませんでした。
奈良時代、平安時代
天平神護2年(766年)に勝道上人が日光を開山して、延暦元年(782年)に輪王寺の前身である四本龍寺を建てました。神護景雲元年(767年)に勝道上人は大谷川の北岸に二荒山大神を祀り、日光は山岳信仰の聖地として崇拝されるようになりました。
元暦2年(1185年)に平家が滅亡すると、平家一門は散り散りに各地に逃げ延びました。平貞能は妙雲禅尼と平資盛とともに湯西川に落ち延びたとの伝説が残ります。
鎌倉時代、南北朝時代
治承元年(1177年)に座主を巡る争いが起こり日光山が荒れましたが、承元4年(1210年)に弁覚が座主となり復興しました。鎌倉将軍家は日光山に対して篤く信仰して影響力を強め、南北朝時代に日光山は天皇家の南朝方に与しました。
室町時代、安土桃山時代
天正18年(1590年)に豊臣秀吉は小田原北条氏への加担を理由に日光山の所領を没収しました。
江戸時代
慶長18年(1613年)に日光山貫主に就任した慈眼大師天海は、元和3年(1617年)に初代将軍徳川家康の霊柩を日光山に遷座しました。東照宮が建立されると日光街道、例幣使街道、会津西街道が結節する門前町として栄え、松平正綱は寛永2年(1625年)から参道に杉を植えました。
 徳川家光が絢爛豪華に造り替えました
徳川家光が絢爛豪華に造り替えました
 24年かけて2万本以上の杉が植樹されました
24年かけて2万本以上の杉が植樹されました
3代将軍徳川家光は徳川家康を強く信奉しており、寛永13年(1636年)に日光東照宮の社殿のすべてを建て直しました。家光は家康の近くで眠ることを願い、日光山輪王寺に葬られ廟所は大猷院と名付けられました。大猷院は日光東照宮を凌がないよう金と黒を使用した重厚な落ち着いた造りです。
 3代将軍徳川家光が眠る廟所です
3代将軍徳川家光が眠る廟所です
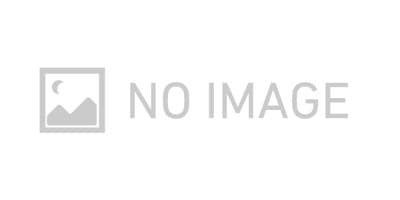 徳川家光に殉死した譜代家臣の墓地です
徳川家光に殉死した譜代家臣の墓地です
慶長15年(1610年)に発見された足尾銅山は天海の所領として、慶長18年(1613年)に日光山光明院になり、元和3年(1617年)には日光東照宮神領となりました。天海が亡くなると正保4年(1647年)に幕府直轄領となりました。
 昭和時代まで採掘が行われました
昭和時代まで採掘が行われました
 五十里洪水により発見された温泉です
五十里洪水により発見された温泉です
天和3年(1683年)に発生した天和日光地震で男鹿川が堰き止められて五十里湖が形成されました。享保3年(1718年)に五十里湖が決壊して五十里洪水を引き起こし大きな被害を与えた一方で、偶然にも川治温泉が発見されました。川治温泉は元禄4年(1691年)に発見された鬼怒川温泉とともに名湯として知られるようになり、傷は川治、火傷は滝(鬼怒川温泉)と称されました。
 東京の奥座敷と呼ばれています
東京の奥座敷と呼ばれています
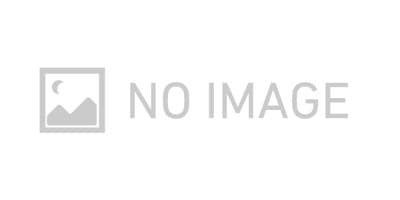 息子二宮尊行とともに日光の開発に心血を注ぎました
息子二宮尊行とともに日光の開発に心血を注ぎました
荒廃した日光神領は、嘉永6年(1853年)に二宮尊徳が農村復興事業のため赴任しました。二宮尊徳は報徳役所を建て田畑や用水路などを建造し、日光神領の建て直しに心血を注ぎました。安政3年(1856年)に尊徳が死去すると、息子の二宮尊行が継承して開発を進めました。
明治時代、大正時代、昭和時代
幕末の戊辰戦争では、明治元年(1868年)に幕府軍が宇都宮から日光山へ敗走しました。幕府軍は会津軍と合流して小原沢で白兵戦となりましたが、新政府軍の板垣退助が日光山内に籠る幕府軍に撤退を交渉させ、日光の町は戦火を免れました。
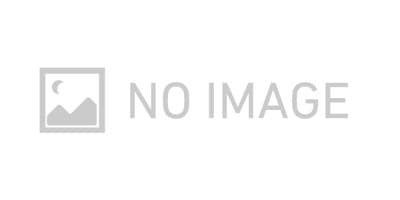 本山坑と小滝坑が連結した基幹坑道です
本山坑と小滝坑が連結した基幹坑道です
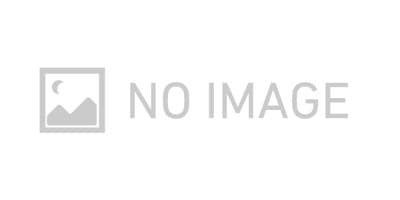 坑道開鑿に使うダイナマイトを保管していました
坑道開鑿に使うダイナマイトを保管していました
明治10年(1877年)に古河市兵衛により足尾銅山が民営化されると、最新の技術や設備により急速な発展を遂げて日本一の銅山に成長しました。足尾銅山は日本の近代化に大きく貢献しましたが、次第に鉱毒被害が問題視されるようになりました。栃木県出身の政治家田中正造は、明治34年(1901年)に天皇直訴事件が起こしました。

 四本龍寺を原点としている寺院です
四本龍寺を原点としている寺院です 日光山岳信仰の中心的な神社となりました
日光山岳信仰の中心的な神社となりました
