栃木県宇都宮市

宇都宮市は栃木県のほぼ中央の肥沃な関東平野のほぼ北端に位置します。鬼怒川水系を中心とした良好な水田地帯が広がります。宇都宮市は餃子専門店がひしめくジャズの町として知られる栃木県の県庁所在地です。
- 面積
- 416.85km2
- 人口
- 515,201人(2022年)
- 市の木
- イチョウ
- 市の花
- サツキ
- 市民の日
- 4月1日
- 地図
宇都宮市を巡る歴史
宇都宮市は旧石器時代から人が生活していました。崇神天皇の皇子豊城入彦命が入り開拓を進め、大和王権の文化が入り込み多くの古墳が造らるようになりました。二荒山神社が造営されると門前町として町が成長し、交通の要衝として宇都宮城の城下町が整備されました。明治時代になると軍都となり二荒山神社の麓には繁華街となりました。
旧石器時代、縄文時代、弥生時代
大陸からナウマンゾウやオオツノジカなどの動物を追いかけて日本列島に人が住み始めるようになり、飛山城跡には動物を追い込む落とし穴と思われる遺構が発見されました。大谷寺洞穴遺跡のような洞窟を利用した生活のほか野沢遺跡のように台地に竪穴住居を建てて住むようになりました。
 洞穴には磨岩仏があります
洞穴には磨岩仏があります
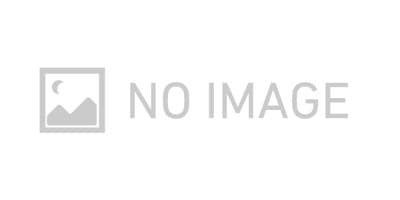 縄文時代の大規模な集落でした
縄文時代の大規模な集落でした
根古谷台遺跡からは他地域との交流で首飾りや耳飾りなどの装飾品を得て、縄文時代中期には竹下遺跡や御城田遺跡等で大きな集落が形成されました。
古墳時代、飛鳥時代
蝦夷を平定するために宇都宮に入る崇神天皇の皇子豊城入彦命は、池沼が多くて池辺郷とも呼ばれていた宇都宮を開拓して開祖となりました。豊城入彦命の偉業を偲び二荒山神社が創建すると、二荒山神社の門前町として栄えました。
 皇子豊城入彦命が宇都宮を作りました
皇子豊城入彦命が宇都宮を作りました
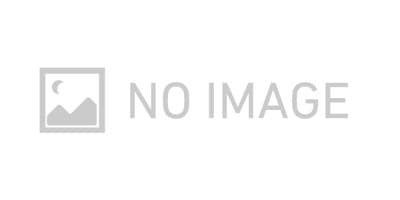 5世紀に造営された前方後円墳です
5世紀に造営された前方後円墳です
大和王権との交流が始まり、4世紀には大日塚古墳、愛宕塚古墳、権現山古墳の3基の前方後方墳がつくられ、5世紀には笹塚古墳、塚山古墳、雀宮牛塚古墳の前方後円墳が造営されました。茂原古墳群からは東海や北陸などの外来系の土器が出土しています。
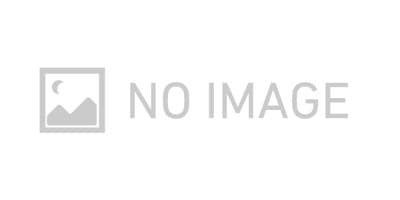 帆立貝式前方後円墳です
帆立貝式前方後円墳です
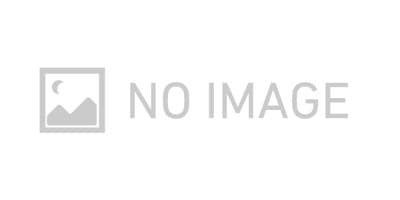 帆立貝式前方後円墳です
帆立貝式前方後円墳です
古墳時代後期の6~7世紀には、宇都宮北部丘陵上に瓦塚古墳群や戸祭大塚古墳などの横穴式石室をもつ多数の古墳群が築造されました。
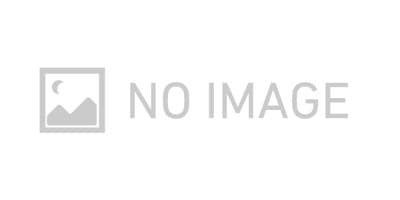 6世紀後半の大型の円墳です
6世紀後半の大型の円墳です
 横穴墓がハチの巣のようにあります
横穴墓がハチの巣のようにあります
長岡では凝灰岩から成る丘陵の斜面にハチの巣のように横穴墓がつくられ、長岡百穴古墳と呼ばれています。扉石をはめた切込みがあり、当時はほとんどの横穴に扉石がありました。これらの横穴には観音像が刻まれており、地元では弘法大師が一夜で刻んだとの伝承が残ります。
奈良時代、平安時代
8世紀に日本が律令国家として中央集権体制が確立すると、宇都宮市のあたりは河内郡となり上神主・茂原官衙遺跡に郡の役所が置かれました。交通整備のため東山道が整備され、水道山には官衙や下野薬師寺に使用される瓦を焼く窯が置かれました。
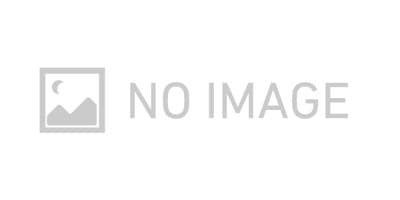 河内郡の役所が置かれました
河内郡の役所が置かれました
 弘法大師により磨岩仏が造られました
弘法大師により磨岩仏が造られました
弘仁元年(810年)の頃に弘法大師により大谷磨崖仏がつくられ、この頃にこの地域の守り神として二荒山神社の社殿が造営されたと言われます。二荒山神社は承和5年(838年)に現在の地に遷されて信仰を集めました。
鎌倉時代、南北朝時代
平安時代末期に二荒山神社の神官を兼ねて政治と宗教を掌握した藤原宗円は、康平6年(1063年)に宇都宮城を築城して二荒山神社の社号宇都宮を姓として宇都宮氏を名乗りました。宗円は鎌倉幕府の中枢で治世を挙げ、弘安4年(1281年)には宇都宮貞綱が九州で元軍の防備にあたりました。文武に秀でた宇都宮氏は、弘安6年(1283年)に宇都宮景綱が宇都宮弘安式条を制定しています。
 宇都宮氏の居城として築城されました
宇都宮氏の居城として築城されました
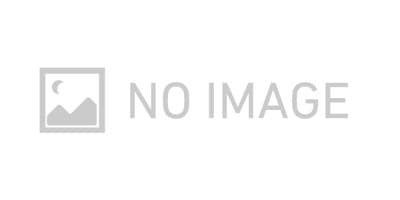 平安時代の集落に城が築かれました
平安時代の集落に城が築かれました
南北朝時代には宇都宮氏綱が足利尊氏を助けたことで上野国と越後国の守護職となりましたが、宇都宮城を牽制するために鬼怒川の東側の高い崖の平安時代初期の集落に永仁年間(1293年~98年)に芳賀高俊が飛山城を築きました。宇都宮の周辺では戦乱が続いたため、宇都宮の町は荒廃しました。
室町時代、安土桃山時代
妙哲禅師は黒羽町の雲巌寺で仏国国師の弟子となり、伝法寺や同慶寺などを開いて下野国に臨済宗を広めました。妙哲禅師は貞和5年(1349年)に亡くなり貞和4年(1348年)に後醍醐天皇が開基した伝法寺に葬られました。
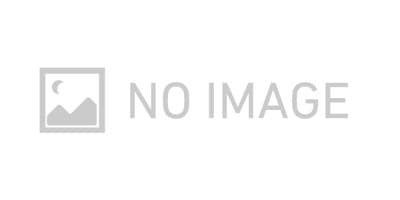 下野国に臨済宗を広めました
下野国に臨済宗を広めました
 宇都宮氏は改易されて城主が代わりました
宇都宮氏は改易されて城主が代わりました
天正20年(1592年)に宇都宮国綱が秀吉の命により朝鮮に出兵しましたが、慶長2年(1597年)に豊臣秀吉から突然の改易を言い渡され宇都宮氏による統治は終わりました。宇都宮城は五奉行の浅野長政が預かり、慶長3年(1598年)から蒲生秀行が宇都宮城主となりました。慶長5年(1600年)の関ケ原の戦いでは、上杉景勝を征伐する徳川秀忠が宇都宮に入りました。
江戸時代
元和5年(1619年)に宇都宮城主の本多正純が城下を整備して領内総検地を始めました。宇都宮は参勤交代や日光東照宮の造営などにより日光街道、奥州街道の宿場町として賑わいました。元和8年(1622年)に本多正純改易されて奥平忠昌が宇都宮に入封し、寛文10年(1670年)に西原・宝木十カ新田の開発を始めています。
宇都宮城主の奥平忠昌が亡くなり下野興禅寺で法要が行われると、奥平家庶流の奥平内蔵允と奥平隼人が口論の末に斬り合いました。内蔵允は切腹となり、寛文12年(1672年)にこれに異を唱えた子源八が江戸の浄瑠璃坂で仇討事件を起こしました。また、宇都宮城主松平忠祇は財政難を理由に上納米を五合摺から六合摺に改め、これに反発した百姓が宝暦3年(1753年)に籾摺騒動と呼ばれる一揆を起しました。
宇都宮で生まれた寛政の三奇人のひとり蒲生君平は、寛政8年(1796年)から荒廃した天皇陵を調査して前方後円墳という名称を始めて使いました。蒲生君平は文化12年(1815年)に設立された藩校修道館、潔身館の設立に参画し、蒲生君平が文化8年(1808年)に著した山稜志に基づき、文久2年(1862年)に宇都宮藩主戸田忠恕が山陵修理を行いました。
明治時代、大正時代、昭和時代
宇都宮の城下町は明治元年(1868年)の戊辰戦争で大半が焼け、明治6年(1873年)に宇都宮県と栃木県が併合して明治17年(1884年)に栃木県庁が栃木から宇都宮に移転されました。明治22年(1889年)には宇都宮町が施行され、明治29年(1896年)に宇都宮が市となると、宇都宮は栃木県の政治経済の中心となりました。
 明治28年(1895)に建てられた商家です
明治28年(1895)に建てられた商家です
 明治28年(1895年)に建てられた教会です
明治28年(1895年)に建てられた教会です
日露戦争で部隊編成が必要となると、宇都宮は経済発展の起爆剤として師団を誘致しました。明治40年(1907年)に第14師団が配置されると、兵士を相手とした飲食店や花柳界が栄えて軍都と呼ばれるようになりました。宇都宮の名物である餃子は、第14師団の兵士たちが伝え広めたと言われています。太平洋戦争末期の昭和20年(1945年)には、軍需工場で働く労働者の住まいを破壊する目的で空襲が起こりました。この空襲により市街地の大半が焼失し、620人以上が亡くなりました。
